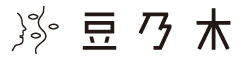マヤビニックの生産者は、メキシコ南部のチアパス州に暮らす先住民コミュニティが主体となり運営される協同組合です。
彼らは伝統的な知恵とオーガニック農法を組み合わせ、標高の高い肥沃な土地でコーヒーを栽培しています。彼らはみずからが暮らす土地や環境に敬意を持ちながら、持続的で環境に配慮した生産方法を守り抜いています。
そうして育まれたコーヒー豆は、主にアメリカや日本国内で高く評価されています。
株式会社豆乃木の創業の「原点」となったマヤビニックコーヒー。
オレンジのような酸と豊かな甘みを持つこのコーヒーは、彼ら先住民たちの自然への敬意が込められた一杯です。



1. 生産地情報
意外と知られていませんが、メキシコは世界最大のコーヒー産地のひとつです。さらに、世界の60%のオーガニックコーヒーは、メキシコで栽培されています。メキシコのコーヒー、特にこれらのオーガニックコーヒーのほとんどは、チアパス州とオアハカ州の小規模農家によって栽培されているのです。そして、このふたつの州はメキシコ国内の中でも先住民が多く住み、経済面では、メキシコ国内でももっとも貧しい地域なのです。コーヒーはメキシコの中でも有数の輸出品で、50万人と言われる小規模生産者と、その家族の生活は、まさにコーヒーに委ねられます。
- マヤビニックの地理的特徴
-
- 所在地: メキシコ南部・チアパス州のアクテアル周辺
- 面積: 1生産者あたり1ヘクタール未満、組合員数は約650家族
- 標高: 標高1,200~1,600メートルの高地。
-
- 自然環境
-
- 地理と気候
チェナロー区はメキシコ南部チアパス州の山岳地帯に位置し、標高は約1,200〜1,600mに及びます。この高地特有の冷涼な気候と適度な降水量(年間降水量1,500~2,500mm)が、コーヒー栽培に最適な環境を形成しています。昼夜の寒暖差が大きいため、コーヒー豆がゆっくり成熟し、甘みや酸味が引き立ちます。 - 土壌と森林環境
火山性の肥沃な土壌が広がり、有機物を豊富に含んでいるため、コーヒーの成長に理想的な環境です。さらに、熱帯雲霧林が多く残り、コーヒー栽培はシェードツリー(木陰栽培)方式が主流です。これにより、土壌の流出防止や生態系の保護が促され、コーヒーの品質向上にもつながっています。 - 生物多様性
チェナロー区は高い生物多様性を誇り、多くの鳥類や昆虫が生息する環境です。特に、コーヒー栽培と共存する形で自然環境を守る取り組みが行われており、オーガニック栽培が推奨されています。 - 社会・文化的背景
チェナロー区にはツォツィル族やツェルタル族などの先住民が多く住んでおり、伝統的な生活様式を守りながら農業を営んでいます。マヤビニック生産者協同組合は、こうした先住民の生活向上や公正な取引を目指し、農家の自立を支援する取り組みを行っています。
- 地理と気候
-
-
2. 商品の背景・ストーリー
- 生産地の背景
- マヤビニックコーヒーが栽培されるチアパス州は、メキシコ国内では経済的に貧しいとされる先住民族人口が多いのが特徴です。メキシコ国家開発計画においても、開発の重要性がうたわれる南東部地域にあるものの、中央政府の支援が行き届かず、貧困指数が最も高い州です。
そのため生産者団体でも、フェアトレードが積極的に推進されています。時代をさかのぼると、1994年1月にはサパティスタ民族解放軍が改善を求めて政府に対し武装蜂起し、国内避難民も発生した歴史を有しています。
- マヤビニックコーヒーが栽培されるチアパス州は、メキシコ国内では経済的に貧しいとされる先住民族人口が多いのが特徴です。メキシコ国家開発計画においても、開発の重要性がうたわれる南東部地域にあるものの、中央政府の支援が行き届かず、貧困指数が最も高い州です。



- マヤビニックと慶應FTPの関わり
- マヤビニック生産者協同組合(Maya Vinic)は、メキシコ・チアパス州の先住民による協同組合で、オーガニックかつフェアトレードのコーヒー生産を行っています。彼らのコーヒーが日本に紹介されるきっかけの一つとなったのが、慶應義塾大学のフェアトレードプロジェクト(Keio Fair Trade Project, FTP) です。
慶應FTPは、山本純一現名誉教授が指揮し、学生主体のプロジェクトで、特にマヤビニックのコーヒーに注目し、輸入・販売活動を行ってきました。2000年代から現地訪問や生産者との交流を重ね、マヤビニックの持続可能な生産を支援しながら、日本市場での認知度向上に貢献しました。学生たちはマヤビニックのコーヒーを学内で販売するだけでなく、フェアトレードの啓発活動を通じて広く紹介し、消費者の意識を高める役割を果たしました。 - その後、慶應FTPを通じて日本国内の企業によりマヤビニックのコーヒーの輸入がおこなわれるようになりました。株式会社豆乃木(まだゆめのつづき)の代表杉山は、慶應義塾大学在学中より慶應FTPの活動に参画。学生理事としてプロジェクトに関わり、卒業後に、活動を継承。独自にマヤビニック生産者との関係を築きながら、継続的なコーヒーの輸入・販売を行うようになりました。
- 株式会社豆乃木では、マヤビニックのコーヒーの輸入・販売を通じて、フェアトレードを実践し、日本国内の自家焙煎店や個人消費者へと販路を拡大しました。また、豆乃木はマヤビニックの生産者との直接的なコミュニケーションを大切にし、彼らの思いや環境を理解しながら、単なる取引ではなく、持続可能な関係を築くことに力を入れています。
- マヤビニック生産者協同組合(Maya Vinic)は、メキシコ・チアパス州の先住民による協同組合で、オーガニックかつフェアトレードのコーヒー生産を行っています。彼らのコーヒーが日本に紹介されるきっかけの一つとなったのが、慶應義塾大学のフェアトレードプロジェクト(Keio Fair Trade Project, FTP) です。

3. サステナビリティへの貢献
- 各種認証(主なもの)
有機(オーガニック)認証
フェアトレード認証
4. 生産者からのメッセージ
マヤビニック生産者協同組合(Maya Vinic)のコーヒーは、自然と調和しながら栽培、収穫されたオーガニックコーヒーです。